暮らしの常識は変わる。〜モビリティ社会と家づくりのこれから〜
2025.09.17
スタッフブログ
Writer
田中 美奈子 一級建築士
暮らしの常識は変わる。〜モビリティ社会と家づくりのこれから〜
ニケンハウジングの田中です。
20年数年前、両親が土地を買って家を建てたとき、目の前にバス停がありました。
けれども当時、働き盛りだった両親にとっては「車さえあれば十分」という感覚が強く、その存在に大きな価値を感じることはありませんでした。
ところが今、両親が高齢となり状況は一変しました。
父は敬老パスを手に、家の前のバス停から1区先のスーパーまで、毎日のように出かけています。20年前には見えていなかった価値が、暮らしの変化とともに浮かび上がってきたのです。
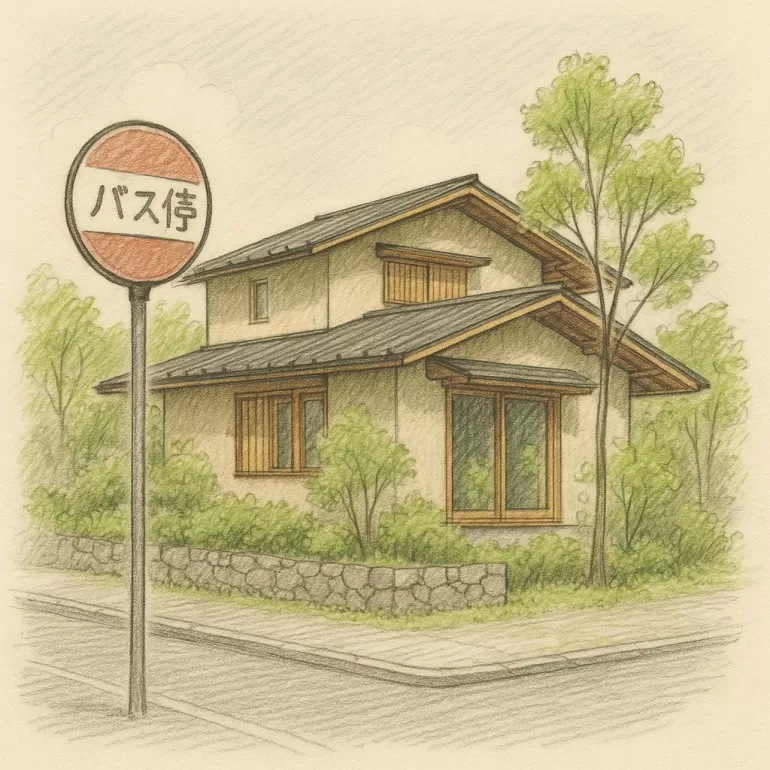
認識の変化に気づき、更に20年後の社会はどうなっているのかを考えました。
例えば今後、自動運転の技術が発展し安価で便利な自動運転タクシーが普及すれば、地方都市においても“1人1台”の車を所有する必要はなくなるでしょう。
未来の暮らしを妄想してみる
さらに未来を想像してみます。例えば、自家用車を持っている人でも、カーシェアサービスに登録して、空き時間だけアプリで呼び出されたクルマが自宅から出発し、稼いで帰ってくる…そんな仕組みが当たり前になっているかもしれません。
もちろん、車内が汚されたり、盗難に遭ったりといった課題はあるでしょう。ですが、技術や社会の仕組みは常に課題を解決しながら進化してきました。20年前にスマホでタクシーを呼ぶことを想像できなかったように、移動の常識も大きく変わっているかもしれないですね。
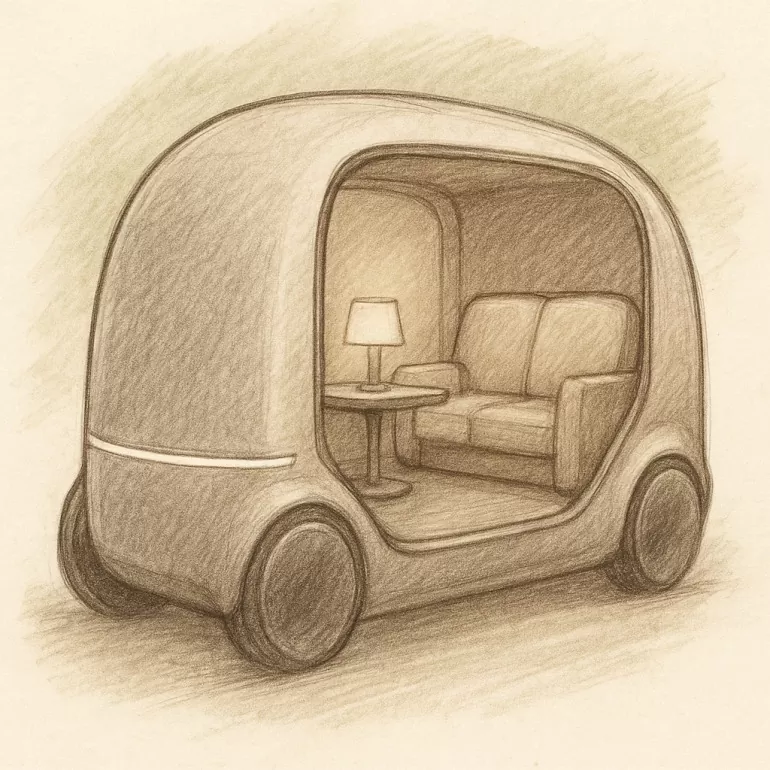
未来の車に運転席の視認性は不要。小さな動くリビングみたいになってたりして。
住宅とモビリティの関係
そんなモビリティの変化は、住宅設計に直結するでしょう。
自動運転のカーシェアやタクシーが普及すれば、家庭ごとの駐車スペースは縮小できる可能性があります。その分を庭に充てたり、そもそもそんな大きな土地が必要なくなるかも知れません。
自宅の駐車場が「シェアカーの基地」になるなど、家がモビリティ社会の接点として機能する未来も考えられます。
「家余り」時代に新たに新築住宅を建てる意味
20年前にはその存在すら意識していなかったバス停が、今では両親の毎日に欠かせない存在になりました。
同じように、今「当たり前」とされている暮らし方も、20年後には同じ価値を持たないかもしれません。
だからこそ、家を考えるときには「今の常識」だけでなく、未来を見据えることが大切です。
それはモビリティに限らず、エネルギー、地域とのつながり、暮らし方の多様性といった要素にも広がります。
空き家問題を抱えた「家余り」の世の中で新築を建てる意味を考えたとき、想像のつかない未来にも柔軟に対応できる可変性のある家づくりは欠かせないと思います。
たった20年での我が家の認識の変化が、ヒントを与えてくれました。
Writer
田中 美奈子一級建築士
一級建築士猫と夫と暮らし、休みの日は日曜大工な、ガテン系主婦です。
猫と夫と暮らし、休みの日は日曜大工な、ガテン系主婦です。
この記事のカテゴリ
